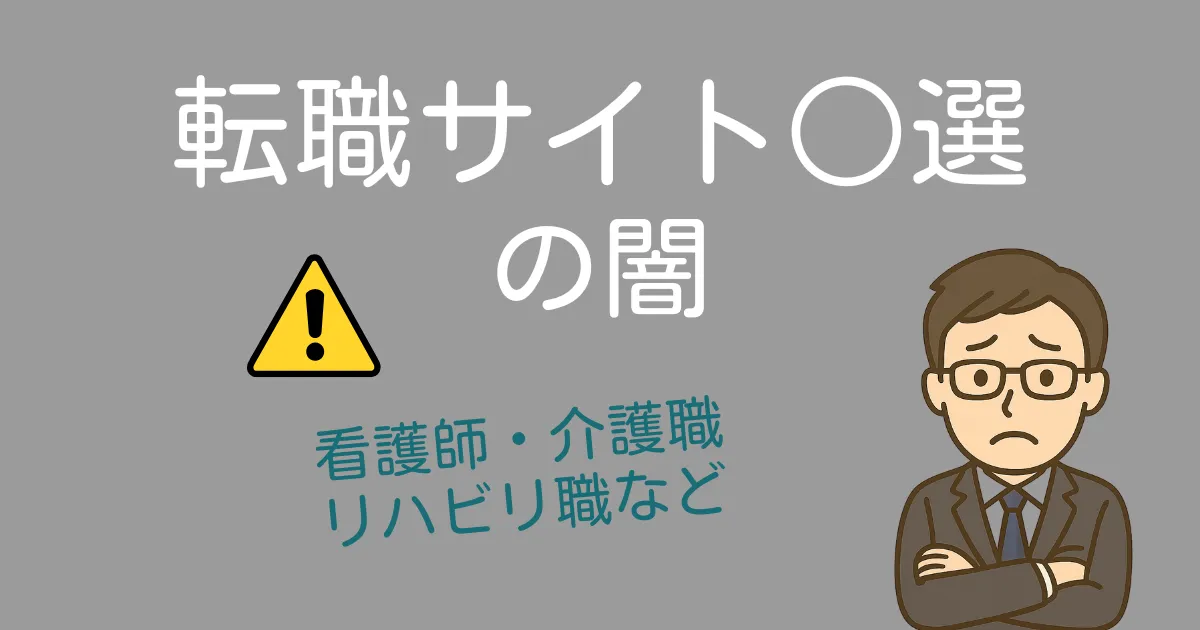はじめに
「看護師 転職サイト」「介護 転職エージェント」などで検索すると、必ず目に入るのが「おすすめ転職サイト○選」という記事。
「10選」「15選」など一見便利そうですが、中身をよく読むと「これって本当に利用者の立場で書いてるのかな?」と疑問に思うことも多いのではないでしょうか。
実はその背景にはアフィリエイト広告という仕組みが深く関わっています。
この記事では、その仕組みと注意点を解説しつつ、皆さんが「損をしないために知っておくべきこと」をまとめました。

この記事を書こうと思ったきっかけは、非公開求人数や求人件数をアピールしているのに、こちらの記事で紹介した厚生労働省職業安定局 人材サービス総合サイトで公表されている数字や、私の法人が取引してきた経験と比べて違和感があったからです。
「転職サイト○選」記事が多い理由
転職サイトやエージェントは、転職活動中の登録者が転職すると企業から紹介料が支払われます。
その一部をブロガーやメディアに還元するのが「アフィリエイト広告」です。
この仕組み自体は悪いものではありません。
ただし、現実としては
- 報酬が発生する会社を優先的に紹介する
- 報酬額が高いサービスをランキング上位に置く
- 「おすすめNo.1」の根拠が不明瞭
といったケースが少なくありません。
つまり、「おすすめランキング=利用者満足度ランキング」ではない可能性があるのです。
よくある「転職サイト○選」の問題点
私が、実際にそういった記事を見て感じた問題点は次のようなものです。
① 実体験が書かれていない
公式サイトに載っている情報をコピーしただけで、実際の利用体験ではない記事が多いです。
そのため「サポートが充実しています」「求人件数が豊富です」といった表面的な言葉に終始してしまい、見ている人にとって有益な情報になっていない場合があります。
② デメリットや注意点が書かれていない
どのサービスにも一長一短があるのに、メリットだけが並んでいる記事も目立ちます。
実際の転職活動では「担当者と合うかどうか」「質はどうか」といったデメリットや注意点を知ることが重要です。
③ 「○選」として数を水増し
「15選」「20選」と数を増やして網羅感を出す記事もありますが、結局どのサービスも似た紹介文で、見ている人が混乱するだけというケースもあります。
私のスタンス:どう紹介しているか
私自身は、次のような基準を大切にしています。
- アフィリエイト案件の有無は関係なく紹介する
- 厚生労働省が公表している客観的なデータも参考にしながら紹介する
- 法人として利用した実感をベースに、体験談も交えて書く
そもそもこのブログは、
人事担当者からみた求人サイト、転職エージェントの実態を知ってもらい、求職者と病院・施設側双方にとって有益な情報を発信したい
と考えて始めています。
紹介している企業の中でアフィリエイトの提携をしてもらえたものについてはアフィリエイトリンクを貼っていますが、忖度はしていません。
アフィリエイト案件があるから紹介をしているのではなく、紹介した会社にアフィリエイト案件があれば提携をしています。

正直なところ、裏話含め本音を書いているので、アフィリエイト案件があっても提携をしてもらえない企業もよくあります・・・笑
(おそらく、「そんなこと書くな」ということなんでしょう)
提携が見送られたとしても、紹介しているサイトのリンクは平等に貼っておきます。
アフィリエイトリンクが混ざっている記事には、記事の冒頭に
記事内に広告が含まれています。
と記載しています。
気をつけるべきポイント
もし皆さんが「転職サイト○選」の記事を読む場合、次の点に注意すると判断を誤りにくくなります。
- 体験談が書かれているか?
→ ただのコピペ記事ではなく、実際に利用した人の声や人事目線の話が入っているか確認。 - デメリットや注意点が載っているか?
→ メリットしか書いていない記事は、広告色が強い可能性大。 - 著者の立場が明確か?
→ 利用経験があるのか、どういった人が書いているのかが不明確なら注意。
特に気を付けるべき具体的なアピール文について理由を含めて紹介していきます。
求人件数○万件!
この数字はまったくあてになりません。
参考にできるとしたら「現在有効な求人数」ですが、これを公表している転職エージェントはありません。
「求人件数の多さ=紹介実績が多い」わけではありませんが、以前も紹介した厚生労働省職業安定局 人材サービス総合サイトで紹介実績が多い転職エージェントは確認することができます。
以下の記事で私がまとめているので参考にしてください。
大手も含めた転職エージェントは、非常に多くの求人情報を自社サイトやIndeed、求人ボックスなどに掲載しています。
ただ、その中には募集中でないものが非常に多く、数年前に募集終了しているものや、法人名以外は架空の求人(実体験)が掲載されていたこともあります。
取引がないのに勝手に掲載していることも・・・。
なぜ、転職エージェントは募集中でもない求人情報をコストをかけてまで掲載しているのか。
それは、見栄えの良い求人、架空の求人など多くの求人情報を掲載していることで求職者の目にとまり、登録してもらうことを目的としているからです。
どれか1つの求人で登録さえしてもらえれば、募集中でなくても次のステップ(電話営業など)に進めるので転職エージェントとしてはまず登録をしてもらいたいわけです。

以前の記事で紹介した求人サイトは、基本的に病院・施設が直接掲載しているのでこういったことはありません。
業界最大級の非公開求人数!
「直接応募が難しいときに考えたい転職エージェントの使い方」でも書きましたが、転職エージェントに本当の意味での非公開で求人を依頼する可能性があるとすれば、看護部長や施設長といった役職者などの特殊な求人です。
ただし、そういった求人を多数抱えている転職エージェントは今まで聞いたことがありません。
ちなみに一般職の求人を非公開で依頼することはあります。
もし、そのことを言っているのであれば(たぶんそのことを言っている気がしますが)、それは私たちが直接掲載している求人情報と競合しないように求人広告を出さないよう依頼しているだけで、病院・施設のホームページやハローワーク、直接掲載に関わっている求人サイトでは普通に公開しています。

転職エージェントがかける莫大な広告費用、SEO対策、おとり広告などにより、私たち病院・施設が直接掲載している求人情報は検索結果の下位になってしまい、求職者の目にとまりづらいんです。
内部情報がわかる!
ほとんどの大手転職エージェントは主要都市(東京・大阪・宮城・福岡など)にしか支店がありません。
日常のやり取りは電話かメールですし、1~2年に一度、1~2人が30分程度訪問してくることはありますが、日程を聞くと2日程度で数施設しか回っていません。
大手転職エージェントであれば1つの支店に多くの営業担当者がいる中で、その程度の訪問で十分に把握できるのか疑問が残ります。
辞めた人から情報が入ることがあると思いますが、基本的に辞めた人は悪く言う傾向がありますし、その人自身がトラブルメーカーだった可能性もあります。
ここで少し内部情報に関する私の経験談を書きます。
近隣に離職が多くて有名なA病院があり、その病院を3ヶ月で辞めたという看護師さんが面接に来たことがあります。
話を聞くと、B転職エージェントに紹介されてA病院へ入職したのですが、離職が多いことなどは全く聞いていなかったそうです。
(私の法人はB転職エージェントからA病院の話を聞いたことがあるため、この情報はB転職エージェントも100%知っていました。)
【参考】
A病院の離職が多いのは、ベテラン看護師数人の態度が悪く、若い看護師や新しく入った看護師へのあたりがきついという理由です。

なぜ、私が理由まで知っているのかというと、
2~3社の転職エージェントと過去に以下のやり取りが複数回あったからです。
どの転職エージェントからも、紹介を受けるにあたって氏名や具体的な病院名を伏せられた「キャリアシート」というものが送られてくる
↓
直近の職歴が短かったりすると、私から「なぜか?」と質問する
↓
「そこは~で離職が多い病院なんです」と回答がある
↓
実際の面接では履歴書に病院名が書かれているので特定できる
という流れです。
面接のときのちょっとした会話でしたが、そういった離職が多い病院の情報を知っていたとしても、転職エージェントが正直に話すとは限らないということが分かります。
なぜなら、A病院もB転職エージェントにとっては良いお客さんだからです。
今回のケースでいえば、A病院はとにかく採用をする必要がある状況なので、内定をもらえる可能性も高く、B転職エージェントとしてはどんどん紹介したいと考えます。
あえてB転職エージェントをフォローすると、
いくら離職率が高い病院であっても、状況や理由によっては「マッチする可能性がある」ので紹介することはあるでしょう。
ただ今回は、結果的に「紹介手数料を得るために営業成績を優先したのでは」と感じるケースでした。
給料交渉もお任せ!
「転職活動でよくある誤解」で書きましたが、特定の状況でもない限り交渉をされたからといって給料を上げることはありません。
「他病院よりも気にいっているけど、少し給料が低いので上がりませんか?」
と言われても、そんな理由で上げてたらその度に他の職員も上げないといけなくなります。
最短○週間で内定も!
他に差別化できないからか、この点を強調していることがありますが、
病院・施設側次第なところもあるので、どこの転職エージェントも同じです。
月給○万円!賞与○ヶ月!好条件多数!
ただの「登録者集めのためのアピール」です。
リクルートダイレクトスカウトなどのハイクラス向け転職エージェントなら分かりますが、医療・介護分野で好条件の求人が特定の転職エージェントに集まることはありません。

本当に好条件で魅力がある求人であれば自然に応募も集まるため、むしろ転職エージェントに依頼しない可能性があります。
それでも「○選記事」は役に立つこともある
ここまで注意点を挙げましたが、すべての「転職サイト○選」記事が無意味なわけではありません。
複数のサービスを知る入口としては便利なので、参考程度に見ても良いと思います。
ただし、大切なのは「記事のランキング=あなたに合ったサービス」とは限らない という点です。
実際の転職活動では、ランキングに振り回されず
- 利用するデメリットも考える
- 実績などは厚生労働省など公的機関が公表しているもので確認する
- 合わないと感じたらすぐに切り替える
- 担当者との相性を重視する
といった使い方が安心です。
まとめ
「転職サイト○選」という記事は、アフィリエイトという仕組みを背景に量産されています。
そのため、内容をそのまま鵜呑みにしてしまうと、「思っていたのと違う」と感じるリスクもあります。
一方で、正しく活用すれば情報収集のきっかけにもなります。
大事なのは、
- ランキングや“おすすめNo.1”を過信しない
- 自分に合うサービスを見極める
- 広告の仕組みを理解して、冷静に利用する
ことです。
私のブログでは、「実際に利用した、契約していたことのある」サービスを本音で紹介しています。
安心してキャリア選びに役立ててもらえたら嬉しいです。