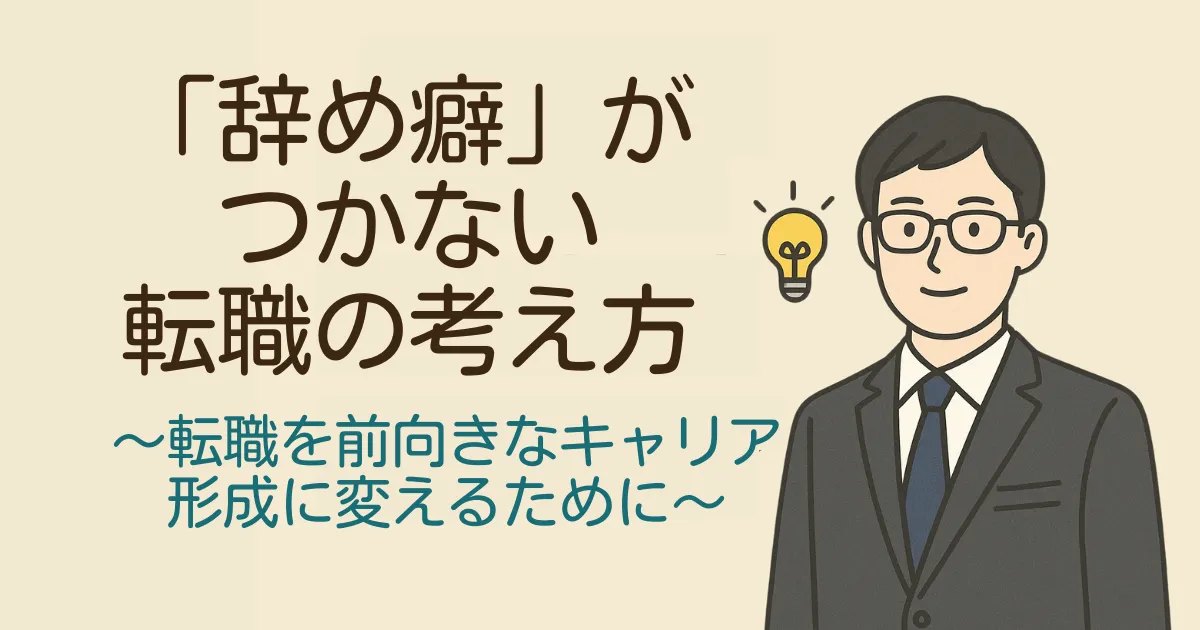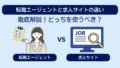はじめに:「辞め癖」って実際どう見られてる?
医療・福祉業界で人事を担当していると、「辞め癖がある人かもしれない」と懸念される応募者に出会うことがあります。
履歴書や職務経歴書に並ぶ短期間の転職歴——
それだけで、評価が下がってしまうのは少し残念なことです。
けれど、現実として「また、すぐ辞めてしまうのでは?」と採用側が不安になるのも事実。
この「辞め癖」という言葉にはネガティブな印象がつきまとうものの、実際には背景も理由も人それぞれ。
本記事では、「辞め癖」と見られないための転職の考え方と、キャリアを前向きに築くためのヒントをご紹介します。
どこからが「辞め癖」と見なされるのか?
目安は「1年未満の転職が複数回」
一般的に、以下のような経歴は「辞め癖あり」と見られることがあります。
- 1年未満の退職が2回以上ある
- 3年以内の職歴が多いのに理由が不明確
- 職種や業界がバラバラで一貫性が見えない
採用側としては、定着率も一つの判断基準として重視せざるを得ないため、短期離職が多いと「またすぐ辞めるかも」という印象を与えてしまいます。

面接での印象が良くても、短期間での離職が多いと採用しづらいと思ってしまうのが本音。
「辞め癖」と見なされないための3つの考え方
① 転職の“軸”を持つ
重要なのは、「なぜ転職するのか」という軸を自分の中に持つことです。
たとえば、次のように自分の判断軸を明確にしましょう。
- キャリアアップをしたい(例:訪問看護にチャレンジしたい)
- 勤務条件の改善(例:夜勤なし、育児との両立)
- 法人の理念や方針とのミスマッチを感じた
単なる不満やストレスのはけ口ではなく、「○○のための転職」と自分でも整理できていれば、他人からも理解されやすくなります。
② 最低でも「やり切った」と思える期間を過ごす
「今すぐ辞めたい!」と思っても、できれば少し踏みとどまって考えてみてください。
特に以下のような条件が揃っていると、転職後の印象がグッと変わります。
- 最低でも1年程度は在職していた
- 何らかの成果や役割があった(リーダー、委員など)
- 退職理由が前向きで、かつ納得感がある

「嫌だったから辞めた」ではなく、「経験を通じて次に進む」というストーリーを作れると、評価はまったく違います。
③ 転職先で“長く働く意志”を明確に伝える
実際の面接では、“これからどう働きたいか”が大事になります。
- 「この法人では長く働きたい理由」を言語化する
- 自分のキャリアプランと法人の方向性が合っていると伝える
- 同じ転職を繰り返したくない意思をしっかり言う
ここまで整理しておけば、たとえ転職回数が多くても、納得感を持ってもらえる可能性は十分にあります。

「今後は長く働きたい」は皆さんおっしゃいますが、説得力を持たせるのが大事!
「辞め癖」を回避する転職活動のコツ
転職の理由を“書く”“話す”準備をしておこう
- 履歴書や職務経歴書には、退職理由を簡潔に記載(書きすぎない)
- 面接で深掘りされても堂々と答えられるよう準備
- 自分の気持ちをノートなどに整理しておくのも効果的
過去をどう見せるかよりも、どう説明し、自分でどう理解しているかが信頼につながります。

理由を深堀りされてつじつまが合わなくなると印象が悪くなるので気を付けて。
情報収集と下調べを徹底する
- 法人の理念・雰囲気・人員構成を事前にチェック
- 評判や口コミだけで判断しない
- 直接応募なら、職場見学を依頼するのもアリ
「入ってからギャップを感じてすぐ辞める」というパターンを防ぐには、事前の見極め力が鍵です。
それでも辞めざるを得ないときは?
もちろん、どうしても辞めざるを得ない事情は誰にでもあります。
心や身体を壊してまで続ける必要はありません。
ただ、「辞める=リセット」ではなく、「次に進む準備」と捉えましょう。
- 一旦リセットしたら、自己分析に時間をかける
- 次は同じ理由で辞めないよう、自分の傾向を知る
- 周囲のアドバイスを素直に取り入れるのも◎
「辞めた自分」を否定せず、ちゃんと見つめ直すことで、次の転職が良いスタートになるはずです。
まとめ:転職を“前向きな選択”にするために
「辞め癖」という言葉に縛られすぎる必要はありません。
けれど、自分のキャリアを信頼してもらうには、計画性と説明力が必要です。
- 多少の短期離職があっても、理由が明確ならマイナスにならない
- 「長く働きたい意思」を行動で示せば信頼される
- 転職は“逃げ”ではなく“選択”であると自信を持とう
あなたの転職が、次こそ「長く働ける職場」に繋がるように。
そのためにも、自分自身としっかり向き合う時間を大切にしてみてください。